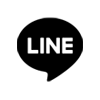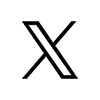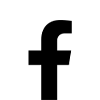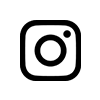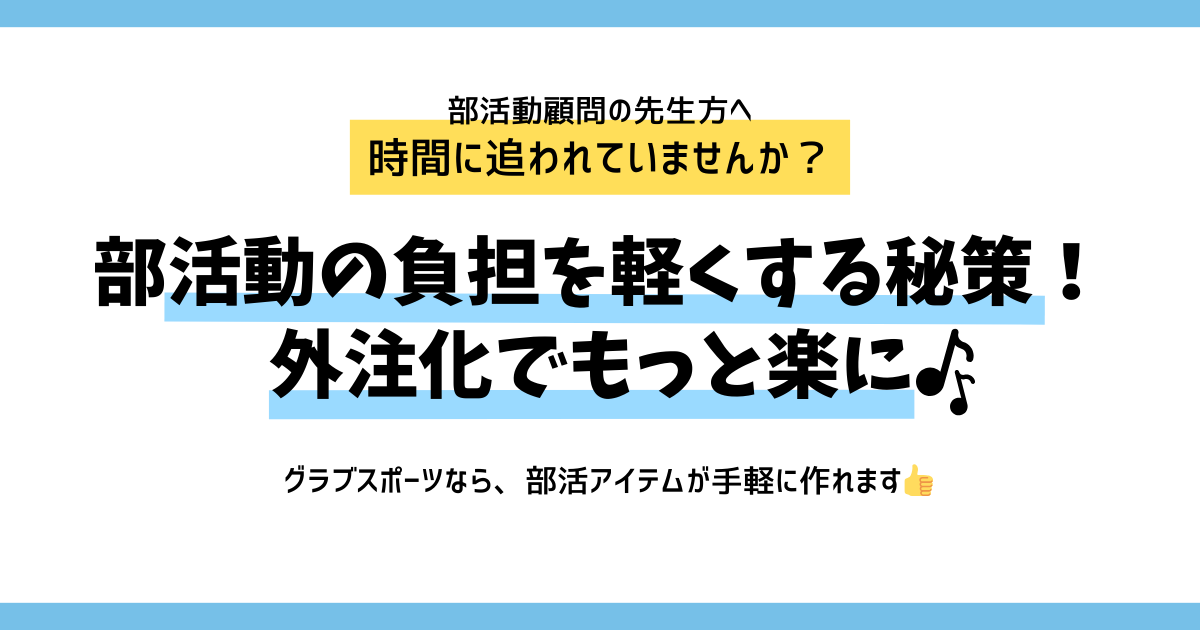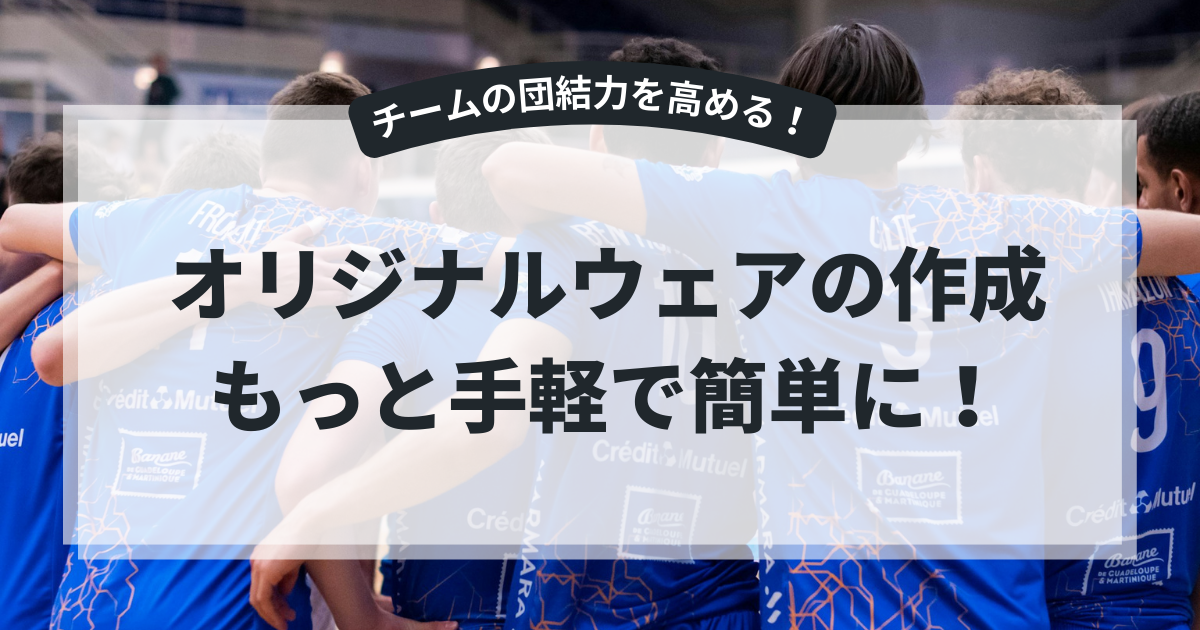「もう疲れた…」をなくそう!翌日に疲れを残さない食事のヒント
スポーツに打ち込む学生アスリートにとって、日々の練習や試合後の疲労回復は、パフォーマンス向上のための最も重要な要素です。
「今日はもう疲れたから、次の練習は頑張れないかも……」という気持ちを翌日に持ち越さないためには、食事によるリカバリーが欠かせません。
忙しい日々の中で「完璧な食事」を目指すことに疲れてしまった保護者や、自炊の難しさを感じている一人暮らしの学生のために、今回もフードコーディネーターの明石が、「回復をしっかりサポートする食事」のヒントとレシピをご紹介します。

翌日に疲れを残さない食事の基本
疲労回復のための食事とは、体内で消耗したエネルギー源と、一時的に傷ついた身体の組織を効率よく補給・修復する食事です。特別な栄養補助食品ではなく、日々の食事から効率的に必要な栄養を摂取してみましょう。
練習後の「枯渇」をすぐに埋める
激しいトレーニング後、身体はエネルギー源である「グリコーゲン」と「水分」を大きく失っています。この枯渇状態を放置すると疲労が残りやすくなります。
炭水化物(糖質)
ご飯やパン、麺類などの炭水化物は、失われたエネルギーを補給し、からだをリセットします。特に練習後30分以内に、おにぎりやバナナなどで素早く補給することが理想的です。
水分とミネラル
汗で失われた水分とミネラル、ナトリウムなどを補給します。味噌汁やスープは、水分と同時に塩分も摂れるため、回復食として優れています。

「修復」と「代謝」をサポートする栄養素
エネルギー補給と同時に、身体の修復作業を助ける栄養素を摂る必要があります。
どんなものを食べると効率が良いか具体的な食品の例も挙げてみます。「グリコーゲン」と「水分」を大きく失っています。この枯渇状態を放置すると疲労が残りやすくなります。
タンパク質
疲労で傷ついた筋肉や、免疫細胞、血液などをつくるための材料です。肉、魚、卵、大豆製品などを毎食欠かさず摂りましょう。
タンパク質
糖質やタンパク質をエネルギーに変えるための「代謝」に不可欠な栄養素です。特に豚肉や魚に多く含まれ、疲労物質の分解を助けます。
抗酸化作用のある栄養素

激しい運動で発生する「活性酸素」によるからだの酸化、イメージで言うとサビを防ぐ、ビタミンC、E、β-カロテンなどを意識して摂りましょう。
具体的には、緑黄色野菜、きのこ類などです。

親子の負担を減らすための食事の考え方

「毎日、バランスの取れた手の込んだ食事を完璧に作る」と思ってしまうと、食事づくりの負担となり、長く続きません。
食事サポートを継続するためのヒントをご紹介します。

Point.1
食事を「準備」ではなく「仕組み」で考える
週末などの時間に余裕があるときに、鶏肉や豚肉を茹でておいたり、野菜をカットしたりする「下準備」をルーティン化しましょう。常備菜や冷凍保存を活用することで、平日の調理時間が大幅に短縮されます。
Point.2
一汁三菜にこだわらない
メインのおかずに、具沢山の味噌汁、一汁二菜や、カット野菜を使った簡単な副菜を添えるだけでも十分です。購入した惣菜をとりれて、品目を増やしても良いでしょう。
Point.3
便利な食材を活用する
ほうれん草、ブロッコリーなどの冷凍野菜や、サバ缶、ツナ缶などなどの水煮缶は、栄養価が高く、包丁も火も使わずにタンパク質やビタミンを補給できる強い味方です。他に、出汁や市販のたれなど調味料などを活用してみましょう。
Point.4
食育の視点を取り入れる
中高生の場合、いずれ一人暮らしや自炊をしなくてはならなくなるかもしれません。口にするもの、献立の決定や簡単な調理、後片付けを選手自身に担当させることで、栄養への意識が高まり、保護者の負担も軽減します。
Point.5
「食べるもの」と「食べたいもの」のバランスをとる
「食べるもの」と「食べなくてはならないもの」にストイックになりすぎず、運動をする本人が「食べたい」と思うメニューも取り入れましょう。精神的な満足感も、回復には欠かせません。

翌日に疲れを残さない!簡単・速攻レシピ3選
ここでは、回復に重要なタンパク質やビタミンB群を補給でき、調理の手間がかからない「簡単・速攻」レシピを3点ご紹介します。
疲労回復の強い味方!豚こま肉のスタミナ炒め
豚肉に豊富なビタミンB1は、糖質を効率よくエネルギーに変え、疲労物質の代謝を助けます。玉ねぎやニンニクと合わせることで、スタミナアップ効果がさらに高まります。
材料(2人分)
| 豚こま切れ肉 | 200g |
| 玉ねぎ | 1/2個 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| ※醤油 | 大さじ1.5 |
| ※みりん | 大さじ1 |
| ※おろしにんにく(チューブ可) | 小さじ1/2 |
| ※和風顆粒だし | 小さじ1/2 |
作り⽅
- 玉ねぎは薄切りにし、※の調味料は混ぜ合わせておきます。
- フライパンに油をひいて中火にかけ、玉ねぎを加えしんなりするまで炒めたら、豚こま肉を加え色が変わるまで炒めます。
- 混ぜておいた※の調味料を加え、強火で一気に絡めます。
- 汁気が飛んで、全体に照りが出たら完成です。
豚肉のビタミンB1が、玉ねぎやニンニクに含まれるアリシンと結合することで、熱に壊れにくくなり、疲労回復効果が長時間持続します。
豚こま肉を使うので、包丁で切る手間がほとんどなく、火が通るのが早いため時短に。ご飯にのせて丼にすれば、これ一品で手早く食事も済みます。
もやしやキノコ類などお好みの野菜を加えてもさらに栄養アップできますよ。
レンジで簡単!サバ缶とたまごのふんわり煮
火を使わず、カンタン3ステップ!電子レンジだけで作れる究極の時短レシピです。サバ缶の良質なタンパク質とDHA・EPAに、たまごを組み合わせて最強バランスの一品を作りましょう。
材料(2人分)
| サバ水煮缶(汁ごと) | 1缶(約160g) |
| たまご | 2個 |
| 酒 | 大さじ2 |
| 醤油 | 小さじ1 |
| 和風顆粒だし | 小さじ1 |
| 水 | 大さじ2 |
作り⽅
- 耐熱容器にたまごを割り入れ、サバ缶(汁ごと)、料理酒、醤油、顆粒だし、水を全て入れ、サバをほぐしながら、よく混ぜ合わせます。
- ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で約2分加熱します。
- 一度取り出し、軽く混ぜて、半熟の状態であればさらに30秒〜1分加熱して完成です。(ラップを外すときは蒸気による火傷に注意しましょう)
サバに含まれるオメガ3脂肪酸は、運動後の筋肉の炎症を鎮め、回復を促す作用があります。卵と組み合わせることで、必須アミノ酸も効率よく補給できます。
包丁、火いらずで、サバ缶の汁をそのまま使うため味付けも失敗しません。疲れて帰宅した日の夜食や、一人暮らしの朝食にもぴったり。
具沢山の回復スープ!鶏むね肉とキノコのミネストローネ風
消化が良く、温かいスープは疲れた胃腸に優しく水分と栄養を同時に補給できます。鶏むね肉とキノコ、野菜をたっぷり入れ、コンソメ味で仕上げました。
材料(2人分)
| 鶏むね肉(皮なし) | 100g |
| キノコ類(しめじ、エリンギなど) | 50g |
| キャベツ | 2枚 |
| 玉ねぎ | 1/4個 |
| 水 | 400ml |
| コンソメ(顆粒) | 小さじ2 |
| 塩、こしょう | 各少々 |
作り⽅
- 鶏むね肉は一口大にそぎ切りにし、キノコ類はほぐします。キャベツと玉ねぎは食べやすい大きさに切ります。
- 鍋に水、コンソメ、鶏むね肉、玉ねぎを入れて中火にかけ、沸騰したらキノコ、キャベツを加えます。
- 野菜が柔らかくなるまで約5〜7分煮込みます。塩こしょうで味を調えたら完成です。
キノコ類に含まれる食物繊維やビタミンD、鶏むね肉のイミダゾールジペプチド、そして野菜のミネラルを煮込むことで、栄養を効率よく吸収できます。
具材を順番に入れるだけで味が決まる煮込み料理は、火加減の心配が少なく、一度に大量に作って翌日の朝食やお弁当にも回せるため非常に便利です。
食事へのプレッシャーをなくし、からだづくりを楽しむために
翌日に疲れを残さないご飯のヒントを掴んでいただくことはできたでしょうか?
学生アスリートや、それを支えるご家族は、毎日の食事、お弁当、補食を完璧にしなくてはというプレッシャーを感じがちです。さらに、栄養や量などを考えると、何をどんなふうに作ったらいいかと悩んでしまうことも。

しかし、「身体をつくる食事」は、特別なものではありません。いつもの食事に、今回ご紹介した食材をプラスしてみましょう。これらは日々、スーパーやコンビニエンスストアで手軽に購入できるものばかりです。簡単な調理でも十分な食事が準備できます。

また、栄養バランスを意識しつつも、たまには手を抜いたり好きなものを楽しんだりすることも大切です。
食事は、「作りやすい」「おいしい」「競技中でも楽しくリラックスできる時間になる」ポイントを見つけることで、気持ちも作ることもだいぶ楽になります。
そんな小さなポイントを、日々の暮らしの中で見つけてみましょう。